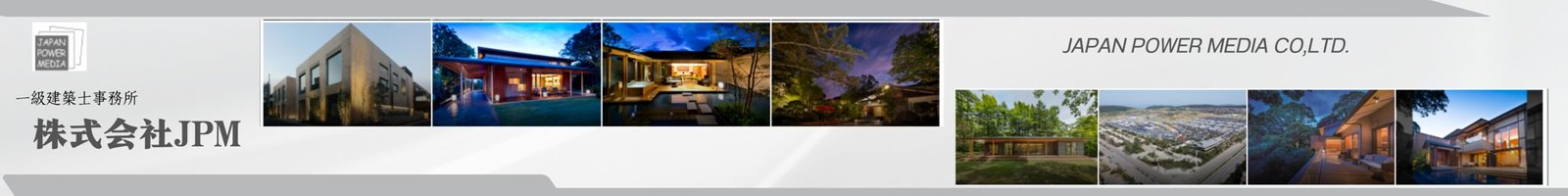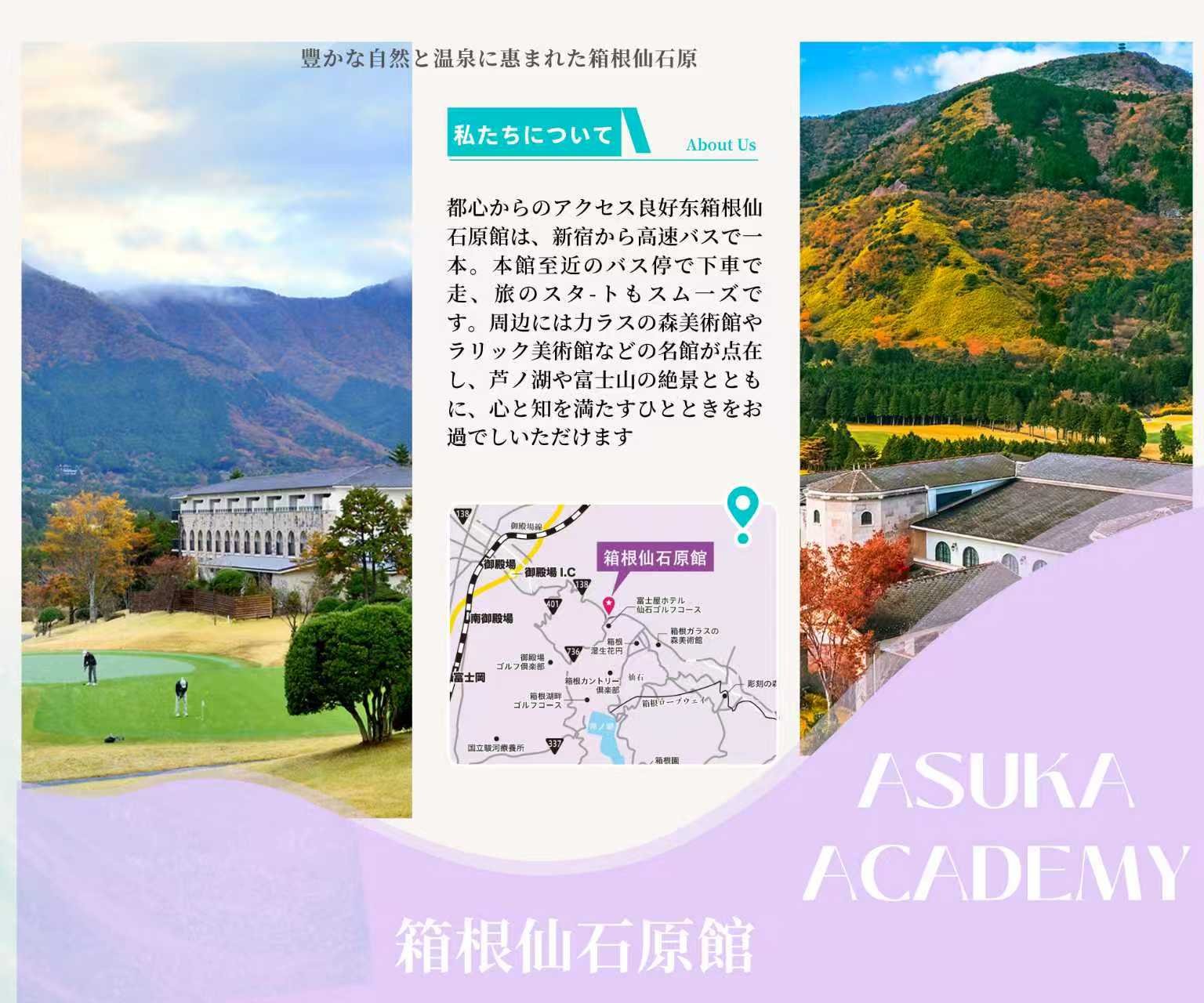(執筆:江華)
トランプが再びホワイトハウスに入ったことを受け、日本外交の船は密かに進路を修正しつつある。
1月28日、石破茂首相は在日華僑華人に向けて春節の挨拶を発表し、「国際情勢はますます厳しく複雑化しているが、分断や対立を克服するために、日本は引き続き他国との対話と協力を行い、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化を図っていく」と述べた。 「他国」の中で最も重要なのは、もちろん米国と中国である。

石破茂は2月6日から8日に訪米し、トランプとの間で日米共同声明を発表する予定がすでに決まっている。 これに先立ち、1月に石破茂は自民党・公明党の幹部を通じて北京を訪問させ、中日執政党交流メカニズムの会議に出席した際、中国国家主席の習近平宛ての親書を手渡し、できるだけ早期に訪中したい旨を伝えた。 これは日本が米中の間である種のバランスを追求していることを端的に示している。 石破茂は1月中旬、マレーシアとインドネシアを訪問した。就任以来、G20やAPECなど多国間首脳会議以外では初の公式訪問となる。 インドネシアのプラボウォ大統領との会談では、石破茂は「日本とインドネシアは非常によく似ており、ともに米国や中国といった大国のはざまでバランスを重視し、その上で外交を進めている」とはっきり述べた。 この発言は、日本の外交戦略の修正とみなされている。安倍政権から岸田政権に至る時期、日本の外交は米国の対中抑止方針に緊密に呼応し、「一辺倒」で米国に追随し、中日関係は冷え込みの底に落ちた。 だが石破政権の下では、日本外交の自主性を強化する方針を強調し、特に対中関係の修復において新たな動きを見せている。外交、文化、政党、軍事、農業など数多くの分野で中日交流が再開または強化され、関係が徐々に解凍されている。 2024年11月以降、中日ハイレベル政治対話メカニズム協議、中日ハイレベル人文交流メカニズム第2回会議、中日執政党交流メカニズム第9回会議が相次いで開催されたほか、中国人民解放軍東部戦区代表団が訪日し、日本の農林水産大臣である江藤拓氏も最近訪中した。中国側は、多・二国間メカニズムに基づく農業分野の各レベル交流を再開し、年内に第10回中日農業次官級会談を開く用意があると明言している。
日本外交が舵を切った理由は、大きく二つある。
一つ目は、トランプ2.0時代の不確実性が非常に大きいことに関係する。トランプは関税の棒を振りかざしてホワイトハウスに戻ってきた。真っ先に狙われたのは中国、カナダ、メキシコであり、日本やEUなどの米同盟国にも寒気をもたらした。 中国と日本はいずれも経済グローバル化の恩恵を受けており、単独主義や保護主義の台頭による圧力に直面している。また両国はいずれも対米貿易黒字国であるため、関税という「ダモクレスの剣」に対して同様の懸念を抱いている。江藤拓農林水産相が「ずっとニュースを緊張して見ていた」と述べたように、トランプが日本農産品に追加関税をかけるのではないかという恐れがあった。 こうした不確実性に対処するために、米国との結びつきを適度に下げ、バランスを取った外交を行うことがベストな選択肢となる。これにより、日本は対米交渉でより多くの手札を持てるようになる。 もし岸田時代のように中米の間でひたすら一方に肩入れして「先兵」となり、米国に振り回されるような状況が続けば、「火中の栗を拾う」ことになりかねず、「アメリカ・ファースト」の犠牲となって中国封じ込めの捨て石にされる危険がある。
二つ目、最も根本的な理由は中日間の巨大な経済的つながりと産業上の相互依存にある。両国の経済は深く融合しており、中日関係の「バラスト」と「推進力」の役割を果たしている。
2024年、中国の対外貿易額は再び過去最高を更新した。その中で韓国が日本を追い抜き、中国の第2の貿易相手国に返り咲いた。中日貿易額は3082.7億ドルで、中韓の3280.8億ドルより約200億ドル少なく、日本にとって大きなプレッシャーとなった。もし日本が好機を逃せば、韓国に追い越される状況が今後も続く可能性がある。 世界的な新たな技術革新と産業変革の波を迎え、中国は「新質生産力」をトップ戦略に位置づけ、「自主的な開放と一方的な開放を秩序立てて拡大する」方針を積極的に打ち出している。 2024年1月15日、中国の李強首相は日本の与党代表団と会見し、中日経済協力の重点領域として、「科学技術イノベーション、デジタル経済、グリーン発展、第三国市場の開拓」などでさらに多くの新たな成長エンジンを共に見出していきたいと明確に述べた。日本はこれらの分野で優位性を持っている。つまり、中日経済・貿易協力は新しい好機を迎えているということだ。 長期にわたり、日本外交には二つの主流思想のせめぎ合いがある。一つは親米主義で、日米同盟至上主義を掲げるもの。もう一つはアジア主義で、日本のアジア大国(時にはアジアのリーダー)としての役割を強調し、中国や韓国、ASEANなど近隣のアジア諸国との関係重視を訴えるものだ。 この二つの思想は常に揺れ動き、消長を繰り返してきた。岸田政権が奉じた「遠交近攻」は前者が優勢となった現れであり、石破茂の「撥乱反正」は後者への一定の回帰である。最初の国賓訪問先としてマレーシアとインドネシアを選んだのもこうした背景を考慮しており、中国との関係修復・緩和も同じ方針に基づく。 2024年以降、中日間のハイレベル接触や各レベル・各分野での往来が絶えず行われており、相互に観光ビザを緩和し、日本産水産物の対中輸入規制緩和も順調に進んでいるなど、中日関係の改善スピードは目覚ましい。2025年に中日間のハイレベル訪問が実現すれば、両国関係に大きな戦略的牽引作用や協力メリットをもたらし、石破政権の外交方針がさらに検証されることになるだろう。