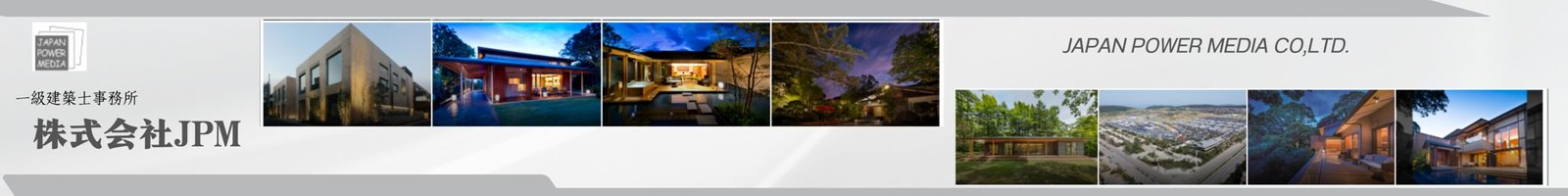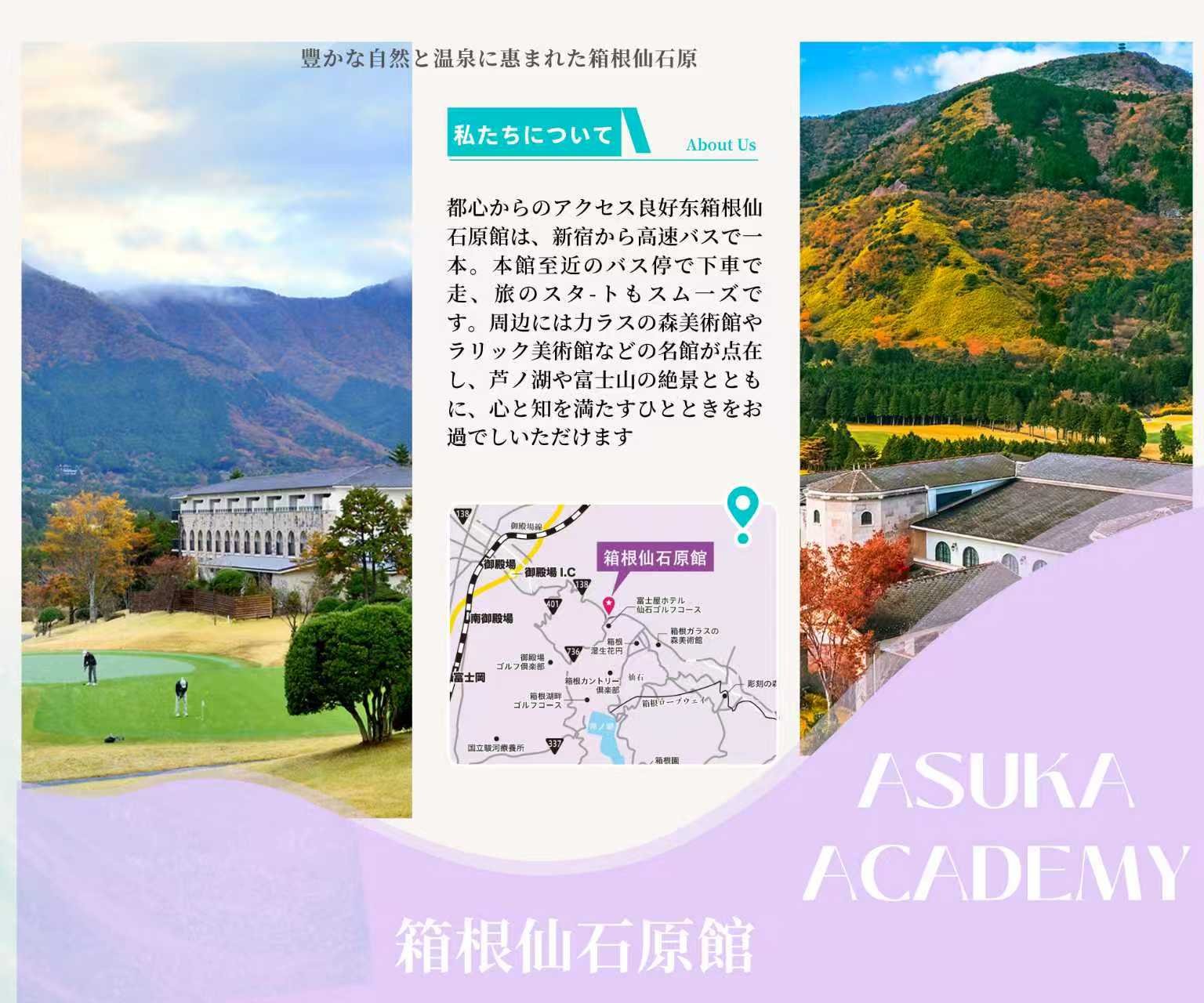4月16日から18日にかけて、日本の経済再生担当大臣・赤澤亮氏が訪米し、アメリカとの初の関税交渉を開始しました。赤澤氏はトランプ大統領、ベセント財務長官、ルートニク商務長官、グリール通商代表などと会談し、日本は関税戦争勃発以来、最初にアメリカと交渉を行った国のひとつとなりました。
今回の交渉で、日本はトランプから関税の「特赦」を得ることはできなかったものの、双方は3つの基本的合意に達しました。いずれも実質的な内容に乏しいものの(建設的な協議を通じて早期合意を目指す、次回交渉を開催することで合意、事務レベル協議を継続するなど)、日米両国ともに今回の対話を前向きに評価しました。日本の石破茂首相は、トランプと赤澤氏の会談に「感謝」を表明し、トランプは今回の協議を「大きな進展」と称し、日本を「最優先の交渉相手」と賞賛しました。世界的に孤立が進む中、トランプは従順な「模範」を作り出すことに躍起になっています。
しかし、日本はトランプが思い描くような「模範生」ではありません。アメリカとの対話を進める一方で、最近では中日関係も再び改善の兆しを見せており、経済分野での対話も次々と行われています。特に3月下旬には、6年ぶりに中日経済高級対話が再開され、サービス貿易、産業、⾃動⾞、食品安全、輸出管理、ビジネス環境、知的財産などの分野で、20項目の合意が成立しました。
このような現実的で柔軟な「レジリエンス外交」は、現在の関税戦争下で石破政権の「三つの不」方針として具体化されています。すなわち、米国製品への報復関税は課さない、米国に対して大幅な譲歩はしない、合意を急がない、という方針です。これは中国の対米報復措置とは対照的であり、日本らしい粘り強さがうかがえます。
中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、第2位の輸出先、最大の輸入元です。一方、アメリカは日本の第1位の輸出先です。中米の対立が激化する中、日本はこのパワーゲームの中で微妙な役割を担っており、輸出依存型経済を支えるためには、どちらの国からの過剰な敵意も回避する必要があります。これは日本のグローバルなサプライチェーンと産業のレジリエンスを維持する鍵となっています。
地政学的には、日本は日米同盟の枠組みの中でアメリカとの安全保障協力を維持しつつ、日中関係の悪化を避けて東アジアの安定を確保しようとしています。トランプは、関税交渉の場で日本により多くの安全保障負担を求め、安全保障問題を交渉の材料にしています。しかし、欧州やカナダ、日本などの伝統的同盟国にまで高圧的な姿勢を見せるトランプの姿勢に、日本国内では安全保障面の不確実性への懸念も高まっています。
日本の公明党幹事長・西田実仁氏は、アジアにおいてOSCE(欧州安全保障協力機構)のような恒常的な協議機構の構築を検討すべきだと繰り返し提言しています。これは緊張時に相互理解を深め、誤解や誤算を回避する手段となるだけでなく、日本の「米国の傘」への依存を軽減することにもつながります。こうした提案は、日本が対中対話と協力を重視する背景ともなっています。
中国国内企業の台頭という厳しい挑戦に直面しているにもかかわらず、日本の多国籍企業は中国市場への投資を緩めてはいません。トヨタ、本田、マツダなどは中国市場における電気自動車生産の体制構築を続けており、華為(ファーウェイ)、百度(バイドゥ)、テンセントなどの中国ハイテク企業との協力も強化しています。また、日系企業の一部は、製造拠点をベトナムやタイなど東南アジア諸国に移転し、米国の関税や輸出規制の影響を回避する一方で、中国市場への輸出能力を維持し、中米いずれかへの過度な依存を避けようとしています。トヨタなどは、アメリカでの現地生産の増加も計画中です。
技術競争の面では、日本は半導体や5G分野でアメリカと協力しつつも、中国市場とサプライチェーンへの依存も避けられません。日本は概ね、アメリカによる対中技術封鎖政策に呼応しており、中国に対しては限定的な協力とリスク管理を両立させる戦略を取っています。たとえば、日本の半導体製造装置メーカーは、米国の「最小含有規則」や「外国直接製品規則」の影響を受けており、アメリカの技術を含む製品を中国に輸出するには許可申請が必要です。これにより、米国の制裁ラインを超えないよう注意しています。
一方で、日本は中韓との三国協力メカニズムを通じて、AIや新エネルギー分野での技術交流を模索しています。4月11日には、7年ぶりに中日韓の情報通信大臣会合が開催され、次世代情報通信技術やデジタルイノベーションの応用について幅広い合意がなされました。
総じて言えば、アメリカによる高関税政策と対中技術封鎖、そして中国の対米報復措置という状況の中で、日本は慎重な外交・経済戦略をもって中米両国との「二面作戦」を模索しています。すなわち、アメリカとの経済協力を深化させ、技術制限に協調し、安全保障同盟を強化する一方で、中国への投資、サプライチェーンの調整、限定的な技術協力を継続し、中米のいずれにも過度に傾かず、バランスを取ることで、主体性を確保し、経済的利益と地政学的影響力を守ろうとしています。
もっとも、こうしたバランスはリスクを伴います。もし中米対立がさらに激化すれば、日本は経済と安全保障の両面で、より明確な選択を迫られる可能性が高まるでしょう。